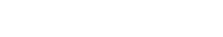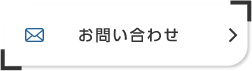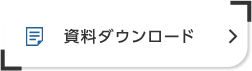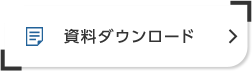【AS platform】年金の繰下げ受給は、本当にお得でしょうか?
共感と学びの募集人プラットフォーム AS platform 2025年7月22日掲載 
公的年金の受給開始年齢は、原則65歳からになっています。ただし、60歳から64歳の間で繰上げ受給をしたり、66歳から75歳までの間で繰下げ受給を選択できることは、ご存知の方も多いでしょう。繰上げ受給の場合はひと月につき0.4%ずつ年金額が減っていきます。仮に60歳0カ月から受給した場合は、65歳から受給するケースに比べて24%ほど減った年金額を受け取ります。減った年金額は、一生変わりません。一方の繰下げ受給は、ひと月ごとに0.7%ずつ、年金額が増えていきます。仮に70歳0カ月から受け取った場合、年金額が42%増額される計算になります。繰下げ受給も、増えた年金額を一生受け取ります。
額面では有利に見える繰下げ受給も手取りでは損になるケースも!
このように額面で見ると、繰下げ受給は有利な制度に思えますが、実は有利とも言い切れないのが現実です。額面が増えても、税金や社会保険料の負担によって、増えた額よりも引かれる額が多くなるケースがあるからです。また、繰下げ受給を選択しなければ、非課税者でいられたのに、繰下げ受給を選択したため、課税者になる場合は特に注意が必要です。 非課税者が課税者になると、さまざまな減免制度の対象から外れてしまいます。たとえば、国民健康保険料や公的介護保険料などの負担についても減免の対象にならなくなるため、支払額は増えてしまいます。また、ひと月にまとまった医療費がかかったときに適用される高額療養費の所得区分も変わります。 さらには、昨今、国から支給されている臨時の給付金も、非課税者を対象としたものが多いため、それらを受け取る権利も失います。このようなさまざまな制度を考えると、繰下げ受給を選択したことで非課税者から課税者になるケースは、デメリットのほうが大きいことを理解しておくとよいでしょう。
繰下げ受給で額面が増えても税と社保で30%前後は引かれる
もともと課税者の場合はどうでしょうか。課税者というのは、繰下げ受給を選択しなくても、税金を支払っている人です。もともと課税されているのだから、多少、税金や社会保険料を差し引かれても、額面が増えるほうが良いだろうと考える方もいるはずですが、差し引かれる額は多少ではありません。自治体ごとに、国民健康保険料や公的介護保険料の割合は異なりますが、年金額が増えたとしても、増えた額の30%前後は税金と社会保険料で引かれます。たとえば、繰下げ受給を1年間おこない、年間で年金額が8.4%増えたとしても、手取りでは逆転してしまうのです。
※所得税5%、住民税10%で試算したケース。 ※国民健康保険料は所得割にかかわる部分の増額だけを抜き出して試算しているため、表での手取りが少ないとしても、国民健康保険料の総額が高い自治体とは限らない。
さらにもったいないのは、繰下げ受給を選択しているあいだは、公的年金控除の110万円を使う権利を捨ててしまうことです。5年間、繰下げ受給を選択した場合、5年間で550万円もの控除を使わない計算になります。控除は経費と似たような役割をしてくれるわけですから、その権利を放棄してしまうのも考えものだと思います。
以上のようなことから、年金の繰下げ受給の話をするときは、額面が増える話に終始せず、お客様にとって「手取りで有利になるのか、不利になるのか」まで踏み込むことが望ましいでしょう。
AS platform(法人版)へログインして もっと読む
AS platform(個人版)へログインして もっと読む
AS platformの詳細は こちら
AS platform(個人版) 利用登録(無料)は こちら
この記事の著者
ファイナンシャル・プランナー 畠中 雅子
1992年にFP資格を取得し、実務経験は30年を超える。メディアへの掲載件数は1万件を超え、家計管理、生命保険。住宅ローン、老後資金作りのアドバイスが得意。近年は、高齢者施設への住み替え資金アドバイスにも力を入れている。